参考曲(リファレンス)の重要性
「パクリになるくらいだったら既存曲を参考にしない方がいい」と感じる人も少なくないかもしれません。
しかし参考曲を用意することは、完成までのスピードを上げるためにめちゃくちゃ重要です。
それはなぜかというと、楽曲の完成イメージが明確になるからです。ゴール地点が分かっている状態で作曲をしていくので迷子になりにくいでしょう。
特に初心者の人は参考曲がないと楽曲を完成させるのは難しいですし、プロの作曲家であっても参考曲については重視しています。

私は以前、専門学校で作曲・編曲を学んでいたのですが、必ず参考曲を用意するようにしつこく言われていました。
初心者はパクリでも気にしない
作曲やDTMを始めたばかりの初心者の方は、そこまでパクリかどうかについて気にする必要はないと思っています。
なぜなら、真似をすることは成長への一番の近道だからです。
プロの楽曲を聴いて技術を盗む、というのは同時にインプットとアウトプットができるので勉強方法としては最強です。

そして真似することに慣れてきたら、これから紹介する方法を使って自分の個性を足していくのがいいと思います。
そもそもこのような記事を読んでいる時点でパクリかどうかを気にできている、つまり自分の曲を「客観視」できている方々だと思うので、自然とパクリを脱却できると思います。
作曲でお金を稼いでいるとか、本格的にプロを目指しているとかなら話は別ですが、初めのうちはパクリでもいいのではないでしょうか。
参考曲のパクリと言われないための方法
参考曲は複数用意する
まず最初にやるべき方法は参考曲を複数用意することです。
参考曲を複数用意することのメリットは、いろんな曲の特徴を取り入れられるためパクリになりにくいということです。
具体的な参考曲の曲数ですが、2~3曲くらいがちょうどいいと思っています。
音楽系専門学校に通っていた時は3曲くらい用意するように言われていました。
例えばドラムのリズムはこの曲、使っている音色はこの曲、楽曲の構成はこの曲、という感じにそれぞれ参考にする部分を分散させることができます。
メロディは真似しない
リズムや音色などのヒントを参考曲から得られる、とお話しましたが
唯一、メロディを真似することだけはあまりおすすめできません。
一つ目の理由はシンプルに著作権に引っ掛かりやすくなるからです。

作曲者の権利はコード進行やリズムにあるのではなく、メロディにあるため、違法行為に手を染めてしまう可能性があります。
二つ目の理由は、メロディはパクリだとばれやすいからです。
例えばコード進行のパターンはある程度の法則があるので、他人の曲と同じコード進行になってしまう確率も高くなります。
ドラムなどのリズムも同様に、ジャンルによってリズムパターンがある程度限られてきます。
一方メロディに関してはもっと自由で複雑なため、他人とかぶる確率は極めて低くなります。
そのためメロディが似ていると「これはパクリなのでは」と疑いの目を向けられやすいわけです。
使っている音色、楽器を変えてみる
もし楽曲が完成に近づいた段階で、「なんかあの曲に似てるな」とか「パクリみたいになってしまった」と感じたなら
使っている楽器や音色を変えてみるといいかもしれません。

具体的には似てしまった曲で使われていない音を取り入れるのがいいと思います。
例えば作っている曲がaikoさんの「花火」に似てしまったとします。
そこで「花火」では使われていない楽器としてオルガンを追加してみることにしました。
すると少しラテンっぽい雰囲気になってパクリとは感じなくなった、、みたいな感じです。
便利な方法ですが、あくまでも楽曲にマッチする音色を選ぶようにしてください。
リズム(ビート)を変えてみる
音色と同様、楽曲のビートを変えてみることもできます。
ただしビートを変えることは曲の土台となる部分を大幅に変えることになるので、その影響を十分に検討した上で実行してください。
具体的なやり方としてはドラムのパターンを変えるのが一番手っ取り早いです。

例えば似てしまった楽曲が8ビートのドラムパターンだったので、自分の曲は4つ打ちにしてみる
などといった感じです。
個人的にはヒップホップやダンスミュージック系でやることが多いです。
これらのジャンルは「リミックス」という概念があるように、ビートの入れ替えをしてもうまくいく場合が多い気がします。


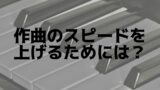



コメント